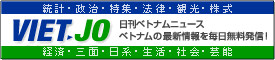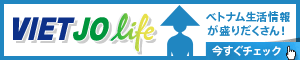ベトナム映画「サイゴン・クチュール」グエン・ケイ監督インタビュー
ベトナム映画界きってのヒットメーカーとして活躍するベトナム人女性監督、グエン・ケイ(Kay Nguyễn)氏が手掛けた「サイゴン・クチュール(原題:Cô Ba Sài Gòn)」が、12月21日(土)より新宿K’s cinema(ケイズシネマ)を皮切りに日本全国で順次公開されます。

アメリカ、イギリス、日本で実績を積んだグエン・ケイ監督。脚本で参加した「ハイ・フォン(原題:Hai Phượng)」ではベトナムの歴代興行収入を塗り替える大ヒットを飛ばし、脚本や監督のほかにプロデューサーとしても活動しています。
「サイゴン・クチュール」のエグゼクティブ・プロデューサーには「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」にも出演し、女優として成功するかたわら製作者としても目覚ましい活躍をみせるゴー・タイン・バン(Ngô Thanh Vân)。コスチューム・デザイナーには同じくベトナムを拠点に世界で活躍するファッションデザイナーのトゥイ・グエン(Thủy Nguyễn)。新世代のトップランナーである女性たちが集結し、ベトナムの伝統的な民俗衣装「アオザイ」をテーマに、現代的でポップなファッション・エンターテインメントを作り上げました。
これまでのベトナム映画のイメージを一新したこの作品は、ベトナム国内で大ヒットを記録。映画に出てくる新しいアオザイが若者の間でも大流行するなど、ファッション界にまで影響を与えました。また、ベトナム国内だけに留まらず、釜山国際映画祭をはじめ各国の映画祭で上映され、喝采を浴びました。
主人公・ニュイ(Như Ý=ニュー・イー)を演じるのは、出演作が歴代興行収入トップ10に並ぶ人気女優、ニン・ズオン・ラン・ゴック(Ninh Dương Lan Ngọc)。アオザイを通して自分にとって本当に大切なものを見つけ、成長を遂げるヒロインを溌剌とした演技でキュートに演じています。
ニュイを助ける青年・トアン(Tuấn=トゥアン)を演じるのは元人気ボーイズグループ「365daband(バーサウナムダバンド)」のエスティー(S.T)。またゴー・タイン・バンもニュイの母親役で出演し、娘に対する愛情ゆえに厳しく接する母親をその確かな演技力で好演しています。他にもベトナム版「パパとムスメの7日間(原題:Hồn Papa Da Con Gái)」のホン・ヴァン(Hồng Vân)、「サイゴン・ボディガード(原題:Vệ Sĩ Sài Gòn)」のジエム・ミー9X(Diễm My 9X)、「ベトナムを懐う(原題:Dạ Cổ Hoài Lang)」のオアイン・キエウ(Oanh Kiều)など人気実力派女優が勢揃い。主題歌を歌姫ドン・ニー(Đông Nhi)が担当し、本編にカメオ出演もしています。
今回、公開を前に日本を訪れたグエン・ケイ監督に、「サイゴン・クチュール」の制作秘話や映画人としての監督の一面、そして続編の構想などについてお話をうかがいました。
(※本記事はベトナムエンタメ情報サイト「A-TIM’s」とベトナム総合情報サイト「VIETJOベトナムニュース」の合同取材によるものです。)

グエン・ケイ監督インタビュー
―――過去にも日本の映画祭などで上映される機会があり、日本でもファンが多い「サイゴン・クチュール」ですが、どういった経緯でこの作品の脚本・監督を手掛けることになったのですか。
私はベトナムの伝統が大好きで、アオザイも、食べ物も好きです。2015年には「カンフーフォー(Kung Fu Phở)」という、フォーに関する映画も脚本で参加しました。この映画のプロデューサーであり、また女優として主役の母親を演じたゴー・タイン・バンさん、そして同じくプロデューサーであり、ファッションデザイナーであるトゥイ・グエンさんのおふたりはとても素晴らしい女性たちで、トゥイ・グエンさんは美術とファッションの分野で、ゴー・タイン・バンさんは映画の分野でそれぞれ力を持っています。この2人が「アオザイの映画を作りたい」というのを聞いて、「私も一緒にやらせてください」と言いました。それで、この作品の脚本と監督を担当することになったんです。
―――今回、題材としてアオザイ、そして1960年代のサイゴンを選んだのはなぜですか。
1960年代は私が一番好きな時代です。音楽ではロックンロールがあり、ビートルズがいました。また、スウィンギング・ロンドンなどもあって、いろいろな変化が政治的にも社会的にも起きていました。フェミニズム、黒人の平等の問題、同性愛が大きく取り上げられたときでもあって、変化の一番多かった年代だと思います。また、1969年は人類が初めて月面着陸をしたというロマンティックな年でもありました。そういうわけで、この時代を今回の舞台に選びました。
アオザイについては、ベトナムの伝統衣装で非常に古いものなのですが、人々はアオザイを革新することはできない、というふうに考えていました。でもそれは私の考えとは違って、私はこれをテーマにして新しいアオザイを描くことができる、と思ったんです。

―――1960年代というと監督ご自身も生まれる前ですが、当時を描くにあたってどのような点にこだわりましたか。
何を描くにしてもリサーチはとても大切で、詳細まで調べます。私にとって幸運だったことは、とても優秀なプロダクションデザイナー、美術の方に出会えたことでした。また、当時のサイゴンに住んでいた人たちにも会いに行って、当時の様子を自分の耳で聞きました。
この映画は制作費自体が限られていたので、なるべくお金がかからないような脚本を書いて、撮影現場は2か所を当時のように再現しました。映画の中の衣装も、色使いなどもプロダクションデザイナーにお任せして作っていきました。
―――アオザイやドレスなど、衣装の柄も色もレトロでとても素敵ですよね。特にタイル柄は、ちょうど作品が公開された2017年ごろからこの柄をモチーフにしたアオザイや小物、カフェなどを現地でよく見かけるようになった気がします。レトロブームの火付け役ともなったこの作品の衣装のこだわりや、エピソードを教えてください。
自分たちがこの作品を作っているときは、「すごく好き!」という感覚しかなかったんですね。ファッションもとてもきれいだし、ゴー・タイン・バンさんも「私にお母さん役をやらせて!」と言ったぐらいなんです。やっぱり皆ああいうファッションが好きで、作っている私たち自身がとても楽しんでいました。そういう想いが自然にエネルギーとして大きくなり、どんどん伝播していき、ヒットにつながったのだと思います。
作っている間は「ああ楽しい!」、「ああきれい!」としか思っていなかったのですが、例えば服以外にセリフも昔のマダムたちが話していたような、ちょっと古い言い方を取り入れたりして。そういうものがトレンドとして生まれて、ひとつの文化になったんじゃないかと思います。

―――「サイゴン・クチュール」はSF要素もあるわけですが、タイムトラベルものにしようと思ったのはなぜですか。
この映画を作るときに、若者にたくさん観てもらえる映画にしようと思ったんです。ただ、今の若者たちにとってアオザイがテーマだとつまらない。でも、ファンタジーはすごく好きなんですよね。なので、今回はタイムトラベルを取り入れました。
―――監督が一番印象に残っているシーン、お気に入りのシーンを教えてください。
一番好きなシーンは、ニュイとアン・カイン(An Khánh、2017年のニュイ)がけんかをするところです。書いていて泣いてしまうぐらい好きです。2人のやりとりをよく聞くと、結局のところアン・カインはニュイ自身であり、他人を責めているんだけれど実は自分自身を責めていて、別人なんだけれど自己批判をしている。(アン・カイン役の)ホン・ヴァンさんも、(ニュイ役の)ニン・ズオン・ラン・ゴックさんも、このセリフを全部きちんと理解してくれて、素晴らしい演技をしてくれたからこそ、このシーンが成功したのだと思っています。

―――監督ご自身についておうかがいします。監督ご自身は、どういった経緯で映画の世界に入られたのでしょうか。脚本家、また監督として映画に携わることになったきっかけなどを教えてください。
小さいときから映画が好きだったんです。19歳の時に脚本家、助監督として「1735km」という作品に携わりました。実はこの映画はあまり成功しなかったのですが、それでも映画を作っていてすごく楽しかった。映画を作るというのは大変ですが、やっぱり楽しいんです。人生をエンジョイすることで良い作品ができると私は思っていて、あれからもう15年、16年経ちましたが、今も変わらずその精神で作っています。
―――監督にとって転機となった作品は何ですか。
自分の作品ではなく、今まで観てきた中で自分の映画人としての転機になったものの1本は、バズ・ラーマン監督の「ムーラン・ルージュ」(2001年公開)です。ミュージカル映画なのですが、映画としての要素も素晴らしいし、歌も素晴らしい。この要素は、今回の「サイゴン・クチュール」にも少し取り入れています。
もう1本はアンドレイ・タルコフスキー監督の「惑星ソラリス」(1972年公開)。スペーストラベルが好きなんですよ。1969年というのは月面着陸の年。だから「サイゴン・クチュール」では1969年を舞台にしているというのもあります。今年は2019年で、人類の月面着陸からちょうど50年。「サイゴン・クチュール」が日本で今年公開されるというのは、とても意味がありますね(笑)。
―――一方で、監督ご自身が手掛けた中で印象的な作品は何ですか。
自分が監督した中では、今年の7月に撮影した作品が特別です。主人公は元々男性で、性転換をして女性になるという実話で、本人がこの話を持ってきてくれたのですが、こういうテーマってセンシティブで、どうしてもゴシップっぽくなりがちですよね。でもそうじゃなくて、コメディタッチでヒューマニズムっぽいものにしたい、そうすればもっと魅力的になる、と思ったので、彼女の話を少しだけ作り変えました。
主人公はスタントマンで、男性なんだけれど女性になりたいという夢がある。でも、殺人現場を目撃してしまい逃げるのですが、見つからないように性転換をする、という話です。この作品は、映画人としての自分に変化をもたらしてくれたわけですが、まずテーマが特別だということ、そして伝えたいことがチープにならないように描くということ。そして、主人公を魅力的に描くということ。観た人にそういうことを伝えるという点が、私にとってとても大きなテーマになった作品です。
映画は2020年のバレンタインの時期に公開される予定です。「自分の人生、自分が運命の主人公になりたければ、変えるために立ち上がろう」というのがこの映画に込めたメッセージ。英語で「When life gives you lemons, make lemonade.(人生にレモンを与えられたなら、レモネードを作りなさい。)」という言葉があって、要するに悪いことがあればそれを良いことに変えましょうという意味なのですが、私は「レモンを与えられたなら、オレンジジュースを作りましょう」というメッセージを伝えたいですね。

―――「サイゴン・クチュール」の話題に戻りますが、続編としてパート2とパート3を考えていらっしゃるとのこと。続編の構想を教えてください。
パート2は、「カリフォルニア・クチュール」です(笑)。これも主人公の成長物語です。アメリカに住んでいる越僑(在外ベトナム人)の女の子が主人公で、お母さんを亡くしていじわるなおばさんと一緒に住んでいるのですが、彼女自身まだ自分が使える「魔法」を知らない、という話。魔法っていうのは、実は代々家に伝わっているアオザイ作りのことなのですが、ベトナムに帰って、母方のおばあちゃんのゴーストに出会い、アオザイ作りを教えてもらうんです。
パート3は、「運命の出会い」がテーマです。日本とイタリアのハーフの女の子と、ベトナムとフランスのハーフの女の子が偶然出会う。日系の子は着物、越僑の子はアオザイの技術が家に代々伝わっているのですが、それぞれ着物が嫌い、アオザイが嫌い。そんな中、2人は京都で偶然出会い、着物の縫い方を学ばなければならない、という状況に陥ります。というのはつまり、昔の京都にタイムトラベルしてしまうんです(笑)。
パート2は2020年3月に撮影して、11月ごろにはできるかな。ちょうど1年後にパート3が完成する予定です。
ベトナムでは特に、映画の世界というと男性社会なのですが、デザイナーのトゥイ・グエンさんに言われたんです。「もしチャンスがあるなら残しておいちゃだめだ」と。今回この「サイゴン・クチュール」が成功したのだから、つながりを大事にして、チャンスを逃さず続けなさい、とアドバイスをもらいました。続編も楽しみにしていてください!
グエン・ケイ監督プロフィール
グエン・ケイ(Kay Nguyễn)
脚本家として活躍し、アメリカ、日本(NHK「kawaii project」)、イギリスで映像分野の実績を積んだ後、ベトナムへ帰国。2013年にチャーリー・グエン(Charlie Nguyễn)監督の「Tèo Em」が大ヒットし、同年に脚本家集団「A Type Machine(エー・タイプ・マシン)」を創設。ゴー・タイン・バン主演のアクション映画「ハイ・フォン(原題:Hai Phượng)」には脚本として参加し、歴代興行収入を塗り替える。一大ブームを引き起こした「サイゴン・クチュール」では脚本と監督を担当。直近ではヴィクター・ヴー(Victor Vũ)監督の「Mắt Biếc」をプロデュースしている。
※脚本家集団「A Type Machine(エー・タイプ・マシン)」
代表のグエン・ケイとオウズリーの女性2人を筆頭に、8人から成る。現在までに9本の作品の脚本を手掛け、いずれも興行収入トップの作品となっており、ベトナム映画の質の向上に大きく貢献している。
「サイゴン・クチュール」あらすじ
1969年のサイゴン。9代続いたアオザイ仕立て屋の娘ニュイは、「ミス・サイゴン」に選ばれるほど美しく、スタイルもファッションセンスも抜群。しかし、1960年代の新しいファッションに夢中で、アオザイを仕立てる母親とは対立していた。ところがある日突然、2017年にタイムスリップしたニュイは、変わり果てた自分の姿と店に対面する。母親が急逝した後に店が傾き倒産、生家も取り上げ寸前の状態だった。そこでニュイは自分の「人生」を変えるべく、現代のファッション業界に潜り込んで奔走する。そして次第にアオザイの魅力と母親の本当の想いに気づいていく―――。ニュイは果たしてなりたかった「本当の人生」を取り戻すことができるのか?
予告編
(※本記事はベトナムエンタメ情報サイト「A-TIM’s」とベトナム総合情報サイト「VIETJOベトナムニュース」の合同取材によるものです。)